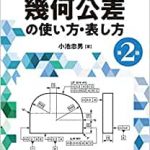その図面、世界で通じますか…?JISでは限界。ISO対応の“幾何公差”スキルこそ、グローバル設計者の必須教養。形状・精度を正しく伝える図面表記の基礎を、体系的に学び直すチャンス。若手設計者こそ今、知っておくべき“国際標準”の描き方を1日で習得できる特別セミナー!!
- 講師
想図研 代表 小池 忠男 先生
日本設計工学会会員
- 日時
- 2025/9/1(月) 13:00〜17:00
- 会場
- 受講料
(消費税率10%込)1名:44,000円 同一セミナー同一企業同時複数人数申込みの場合 1名:38,500円
※WEB受講の場合、別途テキストの送付先1件につき、配送料1,210円(内税)を頂戴します。
- テキスト
- 製本資料(受講料に含む)
受講概要
- 受講形式
会場・WEB
- 受講対象
機械図面を作成する設計者
機械図面を見て製造、あるいは検査に携わる技術者
社内での機械製図規則の作成や制定に携わる技術者
- 予備知識
「機械製図規則」
JIS B 0001「機械製図」があれば理解が進みます。
- 習得知識
1)国際的に通用する「機械製図規則」の概要
2)「サイズ公差」についての基礎知識
3)「幾何公差」についての基礎知識 など
- 講師の言葉
今までの日本の機械図面では、もはや海外(特に欧米)では通用しません。その最大の理由は、「部品形状の表し方」にあります。今までの図面では、部品のあるべき「形状」について、「寸法」と「寸法公差」を用いた様々な指示によって表現してきましたが、形状のあり方を明確に表現するには限界がありました
現在、国際規格ISOでは「寸法」は「サイズ」と「距離」に分類し、「サイズ」に関しては「サイズ公差」で、「距離」については「形状の許容範囲」を含めて「幾何公差」を使って、図面で明確に指示するようになってきています。また、その基になるISO規格もここ数年、多くの新規制定や改定がなされ充実してきています。今後、国際的には、「幾何公差を用いた機械図面」が当たり前となることは必至ですが、しかし、残念なことに現在のJIS規格は、これにほとんど対応できていません。
そこで、このセミナーでは、日本の設計者の多くが抱いている疑問、「なぜいま“幾何公差”を用いた機械図面にしなければならないのか」を詳しく説明し、「幾何公差」の重要性について丁寧に解説します。さらに、それを用いるために必要な基礎事項もしっかり習得していただきます。是非、この機会を逃さずに、「幾何公差を用いた機械図面」の世界を知っていただき、「国際的に通用する機械図面」の作成者、あるいは理解者になっていただきたいと希望しています。
- 進呈
講師著書『実用設計製図 幾何公差の使い方・表し方 第2版』(日刊工業新聞社刊)を進呈します。

プログラム
1.幾何公差の基礎知識
1.1 幾何公差を用いる意義
1.2 幾何公差の種類
1.3 用語と定義、記号と意味
1.4 データムの理解と指示方法
2.幾何公差の指示方法とその解釈
2.1 形状公差(真直度、平面度、真円度、円筒度)の指示方法と解釈
2.2 姿勢公差(平行度、直角度、傾斜度)の指示方法と解釈
2.3 位置公差(位置度、同心度、同軸度、対称度)の指示方法と解釈
2.4 輪郭度(線の輪郭度、面の輪郭度)の指示方法と解釈
2.5 振れ公差(円周振れ、全振れ)の指示方法と解釈
3.演習問題
略歴
1973年 大学院修士課程を修了し、㈱リコーに入社。
20年以上にわたり複写機の開発・設計に従事し、その後、3D CADによる設計生産プロセス改革の提案と推進、
および社内技術標準の作成と制定・改定に携わる。また、社内技術研修の設計製図講師、TRIZ講師などを10年以上務め、
2010年に退社。
ISO/JIS規格にもとづく機械設計製図、およびTRIZを活用したアイデア発想法に関する、教育とコンサルティングを行う
「想図研」を設立し、代表。現在、「幾何公差研究会」(pal@kikaken.jp)の主催、幾何公差に関連する著作、
幾何公差主体の機械図面づくりに関する技術指導、幾何公差に関するセミナー・研修会・講演等の講師活動を行っている。
著書
『幾何公差 データムとデータム系 設定実務』
『幾何公差 見る見るワカル 演習100』
『実用設計製図 幾何公差の使い方・表し方 第2版』
『わかる!使える!製図入門』
『“サイズ公差”と“幾何公差”を用いた機械図面の表し方』(いずれも日刊工業新聞社刊)等。